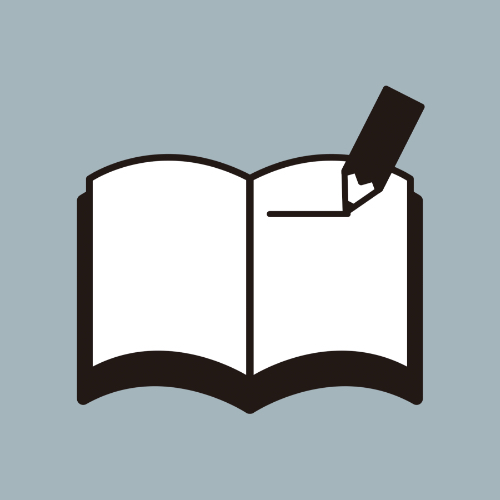このページ内の目次
23節 日本
総論
- 第1 総論
- 日本は温暖な気候のもと人間が状況対応力養成した。また集団状況対応型(状況対応制御ない)が状況対応力養成した。民族状況対応力養成、国家状況対応力養成した(民族、国家発展)。
日本は閉鎖地形(島国)から、人間の状況対応型も集団状況対応型となっている。
自然要因…気候・地形・地質
- 第1 気候…温暖→日本人は状況対応力養成
- 日本は気候が温暖湿潤である。その結果、日本人は状況対応力養成した。そして民族、国家を発展させている。地質も肥沃である。温暖湿潤な気候と肥沃な地質は農耕に適している。
- 第2 地形…閉鎖地形→集団状況対応型
- 日本は、四方を海に囲まれた島国で閉鎖地形である。そのため平和で戦争もなく、民族や国家の設定終了(興亡)。したがって状況対応型は集団状況対応型となった。
- 第3 自然の存続をはかる(自然保護)←自然とともに状況対応
-
-
- 自然の存続をはかる(自然保護)←自然とともに状況対応
- 自然とともに状況対応、生産役務状況対応(集団状況対応の拡大)から自然の存続をはかる(自然保護)。
-
- 植林・公害対策
- 植林をする。水質汚染(川・湖・海)・大気汚染に公害対策をする。
-
人間要因…状況対応型・状況対応力
状況対応型…集団状況対応型
- 第1 状況対応型…集団状況対応型
-
-
- 集団状況対応型
- 閉鎖地形から典型的な集団状況対応型である。
-
- 第2 聖徳太子憲法…集団状況対応型を表す
-
-
- 集団状況対応・対立争い状況対応×…和を以て貴しとなし忤うることなきを宗とせよ
-
-
- 集団状況対応・対立争い状況対応×…和を以て貴しとなし忤うることなきを宗とせよ
- 「和を以て貴しとなし、忤うることなきを宗とせよ」という聖徳太子の言葉がある。集団状況対応(和)すること、対立争い状況対応しないこと(和)を説いている。日本人の集団状況対応型を端的に表している。
-
- 背景…朝廷内対立を抑制・新羅出征中止
- 聖徳太子は朝廷内対立を抑制し、新羅出征を中止した。その中で争いをさけ、日本人本来の状況対応型に復帰することをこの言葉に込めた。
-
-
- 一体状況対応(情報交換+合意)…事独り断むべからず必ず衆と論ふべし
- 聖徳太子の憲法17条に「事独り断むべからず、必ず衆と論ふべし」とある。一体状況対応(情報交換+合意+状況対応)を示している。
-
- 信頼(信用+頼る)…信はこれ義のもとなり
- 聖徳太子の憲法17条に「信はこれ義のもとなり」とある。信頼(集団・構成員を信頼)を示している。
-
- 第3 武士道…集団状況対応型
-
-
- 武士道…集団状況対応型
- 武士道は集団状況対応型の典型である。
-
- 集団状況対応する…国民から尊敬
- 集団状況対した(国民から尊敬)。
-
- 集団状況対応優先
- 集団状況対応を優先する。
-
- 個人状況対応しない←集団状況対応優先
- 個人状況対応しなかった(無私、私心なし、高潔無比)。
-
- 個人成果取得しない←集団状況対応優先
-
-
- 個人成果取得しない…禁欲
- 個人成果取得しなかった(禁欲⇔戦国時代までの武士は恩賞を求める)。
-
- 財産への執着を嫌う・金を卑しむ・金を扱わない・金の話をしない・土地所有を卑しむ
- 財産への執着を嫌った、金を卑しんだ、金を扱わず、金の話をしなかった、土地所有を卑しんだ。
-
- ③金銭重視の取引業者(商人)軽視
- 金銭重視の取引業者(商人)を軽視した。
-
- 取引業者(商人)より貧しくなる
- 取引業者(商人)より貧しくなったが我慢した。
-
-
- 自己制御状況対応←個人状況対応は非本来状況対応
-
-
- 自己制御状況対応←個人状況対応は非本来状況対応
- 個人状況対応は非本来状況対応だから自己制御状況対応した。
-
- 明治維新…武士は自らの地位を捨て武士階級消滅
- 明治維新で武士は自らの地位を捨て武士階級は消滅した。
-
- 武士として習得した学問(教育)で再出発
- 武士として習得した学問(教育)で再出発をはかった。
-
-
- 国民の存続をはかる
-
-
- 国民の存続をはかる
- 国民の存続をはかる。
-
- 大塩平八郎…天保の大飢饉で国民の存続はかる
- 大塩平八郎は天保の大飢饉で国民の存続はかり奉行所と豪商(国民の存続はからない)を襲撃した。
-
-
- 国家設定者子孫の存続をはかる
-
-
- 国家設定者子孫の存続をはかる
- 国家設定者子孫の存続をはかる(楠木正成)。
-
- 楠木正成…後醍醐天皇の存続をはかる
- 楠木正成は後醍醐天皇の存続をはかった。
-
- 幕末…尊皇攘夷運動
- 幕末の尊皇攘夷運動があった。
-
-
- 国家存続が個人存続より優先
-
-
- 国家存続が個人存続より優先
- 国家存続が個人存続より優先する。
-
- 死ぬ覚悟で戦う…楠木正成・西郷隆盛・吉田松陰・葉隠れ
- 死ぬ覚悟で戦う(楠木正成、西郷隆盛、吉田松陰、葉隠れ→武士とは死ぬことと見つけたり)。
-
-
- 第4 五箇条のご誓文・教育勅語
-
-
- 集団状況対応・一体状況対応・集団状況対応優先・自己制御状況対応
- 五箇条のご誓文や、教育勅語にも、集団状況対応、一体状況対応、集団状況対応優先、自己制御状況対応、一体化がうたわれている。
-
戦争時…個人対立争い型・宗教状況対応型の要素
(状況対応型の例外)
- 第1 戦争時…対立争い状況対応の要素
-
-
- 戦争時…対立争い状況対応の要素
-
-
- 戦争時…対立争い状況対応の要素
- 戦争時は、戦争を背景に対立争い状況対応の要素が強くなる。
-
- 鎌倉幕府設定時・室町幕府設定時・戦国時代・幕末明治維新・日清日露戦争
- 鎌倉幕府設定時、室町幕府設定時、戦国時代、幕末明治維新、日清日露戦争時である。
-
-
- 第2 戦国時代の武士…対立争い状況対応の要素
-
-
- 武士…対立争い状況対応
-
-
- 武士…対立争い状況対応
- とくに戦争を担う武士は対立争い状況対応である。
-
- 正しい対立争いとかかげる
- 正しい対立争いとかかげる(大義名分)。
-
- 対立争い状況対応力重視…実力主義
- 対立争い状況対応力を重視(実力主義)。
-
- スパイ…忍者
- スパイをする(諜報、忍者)。
-
-
- 事実に反する状況対応(だまし)
-
-
- 事実に反する状況対応(だまし)
- 戦国大名は事実に反する状況対応(だまし)をした。
-
- 自藩に内通しているとの偽密書を囚人にもたせ殺害…尼子藩内紛
- 自藩に内通しているとの偽密書を囚人にもたせ殺害した(尼子藩内紛)。
-
-
- 対立争い方法習得考案…巧み
-
-
- 対立争い方法習得考案…巧み
- 戦国大名は対立争い対応方法を習得考案していた(巧み)。
-
- 他藩に内部対立をおこさせ乗っ取る…毛利元就
- 他藩に内部対立をおこさせ乗っ取る(毛利元就)。
-
-
- 関係設定の要素
- 主従関係も状況対応合意〈契約〉→農耕地保障と参戦義務〈ご恩と奉公〉、
-
- 強者支配の要素
- 強者支配集団→独裁型の長、状況対応力の養成に熱心、報償・制裁→農耕地付与剥奪)。
-
- 第3 戦国時代の僧・寺…対立争い状況対応
-
-
- 戦国時代の僧・寺…対立争い状況対応
- 戦国時代の僧・寺(宗教集団)も対立争い状況対応となった。
-
- 国家集約対立争いに参加
- 藩と対等な力をもった寺は国家集約対立争いに参加した。
-
- 戦争する…宗派同士の戦争・大名との戦争→信者ぐるみ、焼き討ち、皆殺し
- 戦争をした(宗派同士の戦争、大名との戦争)。戦争も激しい(信者ぐるみ、焼き討ち、皆殺し)。
-
- 宗論…宗派同士の宗教論争
- 宗論をした(宗派同士の宗教論争)。
-
- 小国家長になる…加賀一向一揆
- 小国家長にもなった(加賀一向一揆)。
-
- 第4 戦争後…本来状況対応復活→集団状況対応型
-
-
- 戦争後…本来状況対応復活→集団状況対応型
- 戦争後は本来状況対応が復活し集団状況対応型となる。
-
宗教状況対応型の要素…仏教・キリスト教
- 第1 宗教状況対応型の宗教
-
-
- 宗教状況対応型の宗教
- 例外的に宗教状況対応型の宗教を信仰することがある。
-
- 仏教(自然作動状況受入型)取り入れ…自然の要素がある←自然とともに状況対応
- 自然とともに状況対応するから(3章本来状況対応の拡大・宗教状況対応型の拡大)、自然の要素がある自然作動状況受入型の仏教を取り入れた。
-
- 戦国時代…キリスト教
- 戦国時代のキリスト教がある。
-
高情報養成者…個人対立争い型・宗教状況対応型の要素
(状況対応型の例外)
- 第1 明治以降の情報養成だけの者(高教育養成者)…個人対立争い型・宗教状況対応型の要素
-
-
- 明治以降の情報養成だけの者(高教育養成者)…個人対立争い型・宗教状況対応型の要素
-
-
- 明治以降の情報養成だけの者(高教育養成者)…個人対立争い型・宗教状況対応型の要素
- 情報養成だの者(高教育養成者、インテリ)は、個人対立争い型、宗教状況対応型の要素がある。
-
- 明治政府時代…欧米状況対応取り入れ
- 明治政府時代に欧米状況対応取り入れた。
-
- アメリカ占領軍の強制同化で個人対立争い型・宗教状況対応型を取り入れ
- 戦後のアメリカ占領軍の強制同化で個人対立争い型、宗教状況対応型を取り入れた。
-
- 神決定状況対応型の正しい状況対応取り入れ…正義を取り入れ
- 神決定状況対応型の正しい状況対応を取り入れた。正義を取り入れた。
-
- 神決定状況対応型・神操作状況受入型の神操作状況(神の原理)…原理を取り入れ
- 神決定状況対応型、神操作状況受入型の神操作状況受入型の神操作状況(神の原理)を取り入れた。原理を取り入れた。
-
- 右翼左翼のイデオロギー活動家・共産党・日教組
- 右翼左翼のイデオロギー活動家、共産党、日教組がある。
-
-
- 宗教状況対応型の宗教信仰
-
-
- 神決定状況対応型信仰
- 人生に成功すると神決定状況対応型の宗教を信仰する。
-
- 神操作状況受入型(キリスト教)信仰
- 人生に挫折すると神操作状況受入型(キリスト教)を信仰する。
-
- 新興宗教にも走る…オウム教
- 新興宗教にも走る(オウム教)。
-
-
- 個人対立争い型(暴力団・事件屋)と交流
-
-
- 個人対立争い型(暴力団・事件屋)と交流
- 同じ個人対立争い型の暴力団、事件屋と交流する。
-
- 事件屋が左翼弁護士に依頼
- 事件屋が左翼弁護士に依頼する。
-
-
漁業民族…対立争い状況対応の要素
- 第1 漁業民族…対立争い状況対応の要素
-
-
- 漁業民族…対立争い状況対応の要素
-
-
- 日本は海に囲まれ漁業も盛ん
- 日本は海に囲まれ漁業も盛んである。
-
- 業民族は対立争い状況対応の要素がある←自然・動物と対立争い状況対応
- これら漁業民族は対立争い状況対応の要素がある(自然・動物と対立争い状況対応)。
-
- 礼儀・敬語(他人重視状況対応・他人重視情報流し)にうるさくない
- 礼儀・敬語(他人重視状況対応・他人重視情報流し)にうるさくない。
-
-
- 戦争状況対応力←船を移動手段・銛槍を有する
-
-
- 移動手段を有する…操船
- 漁業民族は船という移動手段を有する(操船)。
-
- 銛・槍(漁具)…武器に応用できる
- 銛・槍(漁具)を有し武器に応用できる。
-
- 戦争状況対応力
- 戦争状況対応力がある。
-
-
- 流通業(貿易)←船での移動性
-
-
- 船での移動性…海運に適する
- 船での移動性を有し海運に適する。
-
- 流通業もできる
- 流通業もできる。
-
- 北前貿易
- 北前貿易がある(長州→北海道)。
-
- 国家同士流通業(貿易)…薩摩の沖縄貿易
- 国家同士流通業がある(貿易、薩摩→沖縄貿易)。
-
-
状況対応力
- 第1 状況対応力養成←温暖気候・状況対応制御がない
-
-
- 状況対応力養成←温暖気候・状況対応制御がない
- 温暖気候、状況対応制御がないから状況対応力養成する(3章状況対応力養成する・状況対応力養成しない)。
-
- 民族状況対応力養成・国家状況対応力養成…民族・国家発展
- 民族状況対応力養成(富民族化・強民族化)、国家状況対応力養成(富国化・強国化)する(民族・国家発展)。
-
状況対応力養成…状況対応養成・情報養成
- 第1 大和政権…状況対応養成
-
-
- 大和政権…状況対応養成
- 大和政権時代は情報養成があまりなく状況対応養成であった。
-
- 中国南朝と国家同士状況対応し朝鮮進出(任那府)
- 中国南朝と国家同士状況対応し朝鮮に進出した(任那府)。
-
- 唐の国家国土取り込み(侵略)を免れた
- 強大国家唐の国家国土取り込み(侵略)を免れた。
-
- 第2 僧…情報養成
-
-
- 僧…情報養成
-
-
- 僧…情報養成
- 江戸時代まで僧(情報養成)が知的指導者であった。
-
- 時代の変革期は…武士(状況対応養成)に取って代られた→鎌倉時代・戦国時代
- ただ時代の変革期は、武士(状況対応養成)に取って代られた(鎌倉時代、戦国時代)。
-
-
- 僧…中国状況対応習得
-
-
- 僧…中国状況対応習得
-
-
- 僧…中国状況対応習得→仏教・生産役務状況対応・国家状況対応・娯楽状況対応(文化)
- 僧は情報養成で中国の状況対応を習得した(仏教、生産役務状況対応、国家状況対応、娯楽状況対応(文化)。
-
- 江戸時代までの先進状況対応
- 江戸時代までの先進状況対応であった(宗教家、生産役務者、官僚、文化人)。
-
-
- 空海…自然作動状況解明
-
-
- 空海…自然作動状況解明→理論体系構築
- 日本人には珍しく自然作動状況(原理)を解明しようとした(理論体系構築)。
-
- 密教…仏教の未解明部分
- 密教(仏教の未解明部分)をかかげた。
-
- 呪術は原理との交信
- 呪術は原理との交信とした。
-
- 現実世界志向
- 現実世界志向であった(仏教は現実逃避〈状況対応しない〉)。
-
-
-
- 寺(僧の集団状況対応)…先進状況対応
-
-
- 寺(僧の集団状況対応)…先進状況対応
- 僧の集団状況対応である寺も先進状況対応であった。
-
- 宗教状況対応以外のこともする
- 宗教状況対応以外のこともした。
-
- 状況対応力養成…状況対応力養成集団(教育機関)・本山は大学
- 状況対応力養成した(状況対応力養成集団〈教育機関〉、本山は大学)。
-
- 生産役務状況対応
-
-
- 生産役務状況対応
- 生産役務状況対応した。
-
- 荘園・金融業
- 荘園をもった。金融業をした。、
-
- 生産役務指導
- 生産役務指導した。
-
- 門前市・座設定…上納金→不遵守は僧兵で制裁
- 門前市・座を設定した(上納金→不遵守は僧兵で制裁)
-
-
- 国家状況対応…奈良仏教
-
-
- 国家状況対応…奈良仏教
- 国家状況対応した(奈良仏教)。
-
- 鎮護国家で国家長・官僚と提携
- 鎮護国家で国家長・官僚と提携した。
-
- 戦争状況対応…僧兵・神人
- 戦争状況対応した(僧兵・神人)。
-
-
-
- 第3 武士…状況対応養成
-
-
- 武士の発生
-
-
- 武士…農耕民が自己造成した農耕地の所有要求(私有要求)するため発生(平安時代・源平)
- 武士は農耕民が自己造成した農耕地の所有要求(私有要求)するため発生した(平安時代、源平)。
-
- それ以前…東北地方征服で発生?
- それ以前に東北地方征服で発生した?。
-
- その後…新興生産役務者(商業・海運業)からも発生
- その後は新興生産役務者(商業、海運業)からも発生した。
-
- 戦国時代…人口増で下位武士(足軽)が増えた(農家の次男以下)→専業兵士が増える
- 戦国時代に人口増で下位武士(足軽)が増えた(農家の次男以下)。専業兵士が増えた。
-
- 戦国時代まで…警察不十分で国民が武装自衛し武士になる者が多
- 戦国時代までは警察不十分で国民が武装自衛し武士になる者が多かった。
-
- その後…警察充実→兼業武士・新規武士制御→刀狩・兵農分離
- その後警察充実したので兼業武士、新規武士は制御された(→刀狩・兵農分離)。
-
-
- 状況対応養成
-
-
- 状況対応養成
- 状況対応養成である。
-
- 旧状況対応・誤状況対応排除
- 旧状況対応、誤状況対応を排除した。
-
-
- 国家状況対応力養成
- 武士は国家状況対応力を養成した。
-
- 生産役務状況対応力養成×
- 武士は生産役務状況対応力養成が不十分で失敗することもあった。
-
- 農耕業重視→工業・流通業(商業)軽視
- 武士は農耕民出身だから、農耕業を重視し工業・流通業(商業)を軽視した(町人軽視)。
-
- 江戸時代…状況対応力養成←国民の支持確保
-
-
- 江戸時代…国家状況対応での対応対立争い状況対応(政争)が禁止
- 江戸時代は国家状況対応での対応対立争い状況対応(政争)が禁止された。
-
- 国民の支持を受けるべく状況対応力養成
-
-
- 国民の支持を受けるべく状況対応力養成
- 国民の支持を受けるべく状況対応力養成に励んだ。
-
- 集団状況対応型養成…武士道
- 集団状況対応型を養成する(武士道)。
-
- 警察能力養成…熊退治
- 警察能力を養成する(熊退治)。
-
-
-
- 第4 鈴木正三…武士として状況対応養成+僧として情報養成
-
-
- 鈴木正三…武士として状況対応養成+僧として情報養成
- 鈴木正三は戦国時代に武士として戦争に参加し状況対応養成であっが、出家し僧として情報養成した。
-
- 本来状況対応集団状況対応型の復活はかる
-
-
- 本来状況対応集団状況対応型の復活はかる
- その結果、本来状況対応の集団状況対応型復活をはかった。
-
- 仏教で集団状況対応型養成
-
-
- 仏教で集団状況対応型養成
- その結果、仏教で集団状況対応型養成した。
-
- 禅で禁欲(個人成果取得制御)養成
- 禅で禁欲(個人成果取得制御)を養成する(人格修養、修行、穏やかな動作も養成)。
-
- 生産役務が仏行
- 生産役務が仏行とした(生産役務する)。
-
-
-
- 第5 江戸時代の取引業者(商人)…状況対応養成
-
-
- 江戸時代の取引業者(商人)…状況対応養成
- 江戸時代の取引業者(商人)は状況対応養成であった。
-
- 信頼取引(先物・為替)開始
- 江戸時代の取引業者(商人)は、早くから信頼取引(先物、為替)を開始した。
-
- 生産役務状況解明…産業原理・合理主義・理論
- 江戸時代の取引業者(商人)は生産役務自然作動状況解明した(産業原理、合理主義、理論)。
-
- 誤状況対応存続させない
-
-
- 誤状況対応存続させない
- 誤状況対応を存続させない。
-
- 山片幡桃…神仏否定
- 山片幡桃は神仏を否定した。
-
- 富永仲基…大乗仏教は変遷仏教
- 富永仲基は大乗仏教は変遷仏教とした。
-
-
- 明治維新で他国状況対応(先進状況対応)取り入れできなかった
-
-
- 明治維新で他国状況対応(先進状況対応)取り入れできなかった
- ただ明治維新では他国との接触がなく他国状況対応(先進状況対応)を取り入れることができなかった。
-
- 三菱に出資しない
- 三菱に出資しなかった。
-
- 幕末志士…他国見学で取り入れ→株式会社取り入れ(渋沢栄一)
- 幕末志士は他国見学で取り入れた(株式会社取り入れ〈渋沢栄一〉)。
-
-
- 第6 幕末志士(下位武士〈足軽〉)…状況対応養成
-
-
- 幕末志士(下位武士〈足軽〉)…状況対応養成
- 幕末志士(下位武士〈足軽〉)は状況対応養成である。
-
- 明治維新
-
-
- 欧米の国家国土取り込みを免れ明治維新に導く
- 幕末志士は欧米の国家国土取り込みを免れ、明治維新に導いた。
-
- 明治維新元勲…他国留学視察(状況把握)→国家状況対応力養成(強国化・富国化)
- 明治維新元勲は、欧米の発展を知ると百聞は一見に如かずと他国留学や視察し(状況把握)、国家状況対応力養成した(強国化・富国化)。
-
-
- 他国との戦争…誤状況対応(攘夷)を存続させない
- 他国との戦争は(長州藩…馬関戦争、薩摩藩…薩英戦争、佐賀藩…イギリス長崎侵略)、誤状況対応(攘夷)を存続させなかった。
-
- 日清日露戦争
-
-
- 日露戦争…対応方法を習得
-
-
- 日露戦争…対応方法を習得
- 日露戦争も対応方法を習得していた(巧み)。
-
- 革命支援しロシア弱国化…明石大佐
- 革命支援しロシア弱国化した(明石大佐)。
-
-
- 犠牲・負担の大きい戦争もしない
-
-
- 犠牲・負担の大きい戦争もしない
- 犠牲・負担の大きい戦争もさけた。
-
- 征韓論(ロシア侵略阻止)おさえる
- 征韓論(ロシア侵略阻止)おさえた。
-
- 戦争しない…日露戦争後日露協商(戦争余力なし)
- 戦争しない(日露戦争後日露協商〈戦争余力なし〉)。
-
-
-
- 幕藩武士と対立
-
-
- 幕末志士…情報養成(教育)に偏らなかった長州藩・薩摩藩・土佐藩
- 幕末志士は情報養成(教育)に偏らなかった長州藩・薩摩藩・土佐藩であった。
-
- 幕藩武士…情報養成→上位武士・教育に力を入れた佐賀藩・肥後藩・会津藩
- 幕藩武士(情報養成、上位武士)は教育に力を入れた佐賀藩・肥後藩・会津藩であった。
-
- 対立争い…幕藩武士は新聞人として明治政府をたたく
- 対立争った。幕藩武士は新聞人として明治政府をたたいた。
-
-
- 第7 軍人官僚…情報養成だけ(高教育養成)
-
-
- 軍人官僚…情報養成だけ(高教育養成)
- 陸軍大学出身のエリート軍人官僚は情報養成だけ(高教育養成)であった。
-
- 第2次大戦敗戦
- 第2次大戦に敗戦した。
-
- 第8 学者・大学卒・知識人…情報養成だけの者(高教育養成者)
-
-
- 学者・大学卒・知識人…情報養成だけの者(高教育養成者)
- 大正時代から、情報養成だけの者(高教育養成、インテリ、知識人、大学卒)がいる。
-
- 欧米状況対応習得
- 欧米状況対応を習得した。
-
- 旧状況対応・誤状況対応を絶対化…欧米状況対応の絶対化→共産主義正・社会主義正
- ただ情報養成だけから旧状況対応、誤状況対応を絶対化する(欧米状況対応絶対化→共産主義正・社会主義正)。
-
- 基本状況対応力×
- ただ情報養成だけから基本状況対応力がない。
-
中国状況対応取り入れ・中国状況対応やめる
- 第1 江戸時代の儒学者…中国状況対応取り入れ
-
-
- 江戸時代の儒学者…中国状況対応取り入れ
-
-
- 江戸時代の儒学者…中国状況対応取り入れ
- 江戸時代の儒学者(朱子学)は儒教(強者支配の国家状況対応関係設定)を取り入れた。
-
- 中国かぶれ・論語最上
- 中国かぶれで論語を最上とした。
-
- 中国は聖人の国・道徳の国
- 中国は聖人の国・道徳の国とした。
-
- 藤原惺窩…中国に生まれなかったことを悔やむ
- 藤原惺窩は中国に生まれなかったことを悔やんだ。
-
- 佐藤直方…夷狄の地日本に生まれたことを悔やむ
- 佐藤直方は夷狄の地日本に生まれたことを悔やんだ。
-
- 荻生徂徠…中国に近い西に転居
- 荻生徂徠は中国に近い西に転居した。
-
- それまで儒教は僧の学問(中国状況対応)にすぎなかった
- それまで儒教は僧の学問(中国状況対応)にすぎなかった。
-
-
- 第2 江戸時代の儒学者…中国状況対応を改造・改良するもの者もいた
-
-
- 江戸時代の儒学者…中国状況対応を改造・改良するもの者もいた
- 中国状況対応を改造、改良する者もいた。
-
- 論語に遡る←朱子学否定
-
-
- 論語に遡る←朱子学否定
- 朱子学を否定し論語に遡った。
-
- 伊藤仁斉
-
-
- 論語…君臣・父子・家族・友人は愛の原理
- 伊藤仁斉は論語は君臣・父子・家族・友人は愛の原理とした。
-
- 理気二元論否定…理は残忍・刻薄の心
- 伊藤仁斉は理気二元論を否定した(理は残忍・刻薄の心)
-
-
-
- 古代王に遡る←朱子学・論語否定
-
-
- 古代王に遡る←朱子学・論語否定
- 朱子学・論語を否定し古代王に遡った。
-
- 荻生徂徠→古代王の制度か儒教の神髄…礼節・音楽・刑罰・政令
- 荻生徂徠は古代王の制度か儒教の神髄とした(礼節・音楽・刑罰・政令)。
-
-
- 日本の神道が本物の儒教・日本が中華
-
-
- 日本の神道が本物の儒教・日本が中華
- 日本書紀をもとに日本の神道が本物の儒教とした。
-
- 山鹿素行の中朝事実…日本が中華
-
-
- 山鹿素行の中朝事実…日本が中華
- 山鹿素行は中朝事実で日本こそ文明の中華とした。
-
- 中国は易姓革命ばかり・日本は天皇のもとに易姓革命なし・中国より聖人の道行われた
- 中国は易姓革命ばかり、日本は天皇のもとに易姓革命なし、中国より聖人の道行われたとした。
-
-
-
- 日本が世界の中心(中国)
-
-
- 日本が世界の中心(中国)
- 日本が世界の中心した。
-
- 山崎安斉…日本高状況対応力養成→日本が世界〈天下〉の中心〈中国〉)
- 山崎安斉は日本高状況対応力養成とした(日本が世界〈天下〉の中心〈中国〉)。
-
-
- 日本が正統中華…日本を中国と名乗る
- 中国を清が支配してから日本が正統中華とする学者がでた(日本を中国と名乗る)。
-
- 第3 国学者…中国状況対応やめる
-
-
- 国学者…中国状況対応やめる
-
-
- 国学者…中国状況対応やめる
- 国学者は中国状況対応をやめた。
-
- 明が異民族の清に国家国土取り込み・強国支配される→国学がおきる
- 明が異民族の清に国家国土取り込み・強国支配されてから国学がおきた。
-
-
- 中国は国家状況対応力養成できていない
-
-
- 中国は国家状況対応力養成できていない
- 中国は国家状況対応力養成していないとした。
-
- 国学者は中国・朝鮮が後進国であることを知る
- 国学者は中国・朝鮮が後進国であることを知った。
-
-
- 賀茂真淵
-
-
- 儒教否定
- 儒教を否定した。
-
- 万葉集をもとに日本の状況対応が正しい
-
-
- 万葉集をもとに日本の状況対応が正しい
- 万葉集をもとに日本の状況対応が正しいとした。
-
- 日本の古道が正しい道
- 日本の古道が正しい道とした。
-
- 天地に自然と存在する大調和
- 天地に自然と存在する大調和とした(人間が自然とともに状況対応)。
-
- 人間の知恵と作為を超えた自然無為の天地自然の道
- 人間の知恵と作為を超えた自然無為の天地自然の道とした(人間が自然とともに状況対応)。
-
- 人間の作った制度規範は人間の小さな知恵の所産
- 人間の作った制度規範は人間の小さな知恵の所産とした。
-
-
-
- 本居宣長
-
-
- 古事記・源氏物語をもとに日本状況対応正
-
-
- 古事記・源氏物語をもとに日本状況対応正
- 本居宣長は日本状況対応正とした。古事記・源氏物語をもとに日本の状況対応が正しいとした。
-
- 源氏物語のもののあわれ…日本状況対応正
- 源氏物語のもののあわれが日本状況対応正とした。
-
- 霊信仰・日本神道…日本状況対応正
- 霊信仰(自然万物に霊性宿る)、日本神道(八百万の神)が日本状況対応正とした。
-
-
- 中国悪状況対応・儒教悪状況対応…漢意(からごころ)・儒意(じゅごころ)
- 本居宣長は中国を悪状況対応とした。儒教を悪い状況対応とした(漢意〈からごころ〉・儒意〈じゅごころ〉)。
-
- 日本正状況対応正…大和心(やまとごころ)・大和魂(やまとだましい)
-
-
- 日本正状況対応正…大和心(やまとごころ)・大和魂(やまとだましい)
- 本居宣長は日本の状況対応を正とした。
-
- 大和心〈やまとごころ〉大和魂(やまとだましい)…正
- 大和心〈やまとごころ〉大和魂(やまとだましい)を正とした
-
- 漢意(からごころ)・儒意(じゅごころ)…悪→濯ぎ去り大和魂を堅く持つ
- 漢意(からごころ)・儒意(じゅごころ)を悪とした(濯ぎ去り大和魂を堅く持つ)。
-
-
-
集団状況対応型の宗教
- 第1 集団状況対応型の宗教
-
-
- 集団状況対応型の宗教
-
-
- 重視(崇拝)・霊信仰・魔力信仰
- 重視(崇拝)、霊信仰・魔力信仰がある。
-
- 平安時代まで盛ん
- 平安時代まで盛んであった。
-
- 状況解明(科学発達)で衰退
- 状況解明(科学発達)で衰退した。
-
-
- 重視(崇拝)
-
-
- 新崇拝…伊勢神宮の建て替え
- 新崇拝(伊勢神宮の建て替え)がある。
-
- 清崇拝
-
-
- 清崇拝
- 清崇拝がある。
-
- 天皇の死亡で遷都←穢れ
- 天皇の死亡で遷都した(穢れ)
-
-
-
- 霊信仰・魔力信仰
-
-
- 霊信仰・魔力信仰
- 霊信仰がある。魔力信仰がある(中国から流入?→教育養成?)。
-
- 貴族…霊信仰
-
-
- 貴族…霊信仰
- 貴族(集団状況対応型〈小国家同士〉で小国家長が国家長集団設定)は霊信仰があった。
-
- 悪霊が戦争おこす
- 悪霊が戦争おこすとする。
-
- 言霊信仰から歌を詠む
- 言霊信仰から歌を詠むとする。
-
- 京都は霊封じ構造・奈良は仏教が霊封じできないと遷都?…井沢元彦
- 京都は霊封じ構造・奈良は仏教が霊封じできないと遷都?(井沢元彦)。
-
-
- 状況解明(科学発達)で衰退
-
-
- 状況解明(科学発達)で衰退
- 状況解明(科学発達)で衰退した。
-
- 武士…霊信仰がない(迷信・幽霊を信じない)・清崇拝もない(戦争の影響?)
- 武士は霊信仰がない(迷信・幽霊を信じない)・清崇拝もない(戦争の影響?)。
-
-
-
- 第2 中国から宗教の流入
-
-
- 中国から宗教の流入
- 中国から宗教が流入した。
-
- 個人対立争い型の宗教
-
-
- 個人対立争い型の宗教
- 個人対立争い型の宗教が流入した。
-
- 儒教…墓(古墳)・神道の礼拝
- 儒教がある(墓〈古墳〉・神道の礼拝)。
-
- 道教…神道の宮・お札
- 道教がある(神道の宮・お札)。
-
-
- 宗教状況対応型の宗教…仏教
-
-
- 宗教状況対応型の宗教…仏教
- 仏教が流入した(仏教→寺・仏像、
-
- 集団状況対応型の宗教と融合…変容
-
-
- 集団状況対応型の宗教と融合…変容
- 集団状況対応型の宗教と融合した(変容、3章宗教状況対応の宗教)。
-
- 成果取得できる(救済論)に変容
- 成果取得できる(救済論)に変容した。
-
- 国家の存続をはかるに変容…国家鎮護→国家長が採用
- 国家の存続をはかるに変容した(国家鎮護→国家長が採用)。
-
-
-
生産役務要因…生産役務状況対応
- 第1 農耕牧畜・工業・役務業・流通業・役務業・資金業まで到達←状況対応力養成
- 状況対応力養成から、農耕牧畜、工業、流通業、役務業、資金業の段階まで到達している。
- 第2 農耕進む・牧畜衰退
-
-
- 農耕進む…気候(温帯モンスーン)が稲作に適する
- 農耕は気候(温帯モンスーン)が稲作に適し生産性が高い。
-
- 牧畜…衰退
-
-
- 牧畜…衰退
- その反作用で牧畜は衰退した。
-
- 仏教の食肉禁止も影響
- 仏教の食肉禁止も影響した。
-
-
- 縄文時代…畑作の可能性
-
-
- 温暖湿潤な気候と肥沃な地質→縄文時代は狩猟採取
- 温暖湿潤な気候と肥沃な地質から縄文時代は狩猟採取とされる。
-
- 畑作の可能性
- しかし畑作(陸稲、雑穀)もあった可能性がある。
-
-
生産役務状況対応力養成
- 第1 生産役務状況対応力養成←本来状況対応
- 本来状況対応だから生産役務状況対応力を養成する。
- 第2 農耕の集約化
-
-
- 農耕の集約化
-
-
- 平安時代…農耕地造成で集約化
- 平安時代は農耕地造成で集約化した。
-
- 室町時代…鉄農具大量普及で集約化
- 室町時代は鉄農具大量普及で集約化した。
-
- 江戸時代…灌漑・干拓による農耕地造成で集約化
- 江戸時代は灌漑・干拓による農耕地造成で集約化が進んだ。
-
- 集約化→大量生産で農耕業から余剰人員が発生→工業・流通業も発展
- 集約化による大量生産で農耕業から余剰人員が発生し、工業・流通業も発展した。
-
-
- 江戸時代…都市近郊農耕←都市に消費者・流通業者
- 都市に消費者・流通業者が集まったため都市近郊農耕が進んだ。
-
- 第3 工業の集約化
-
-
- 明治維新の国家状況対応力養成(富強国化・国家集約)→工業の集約化
- 明治維新の国家状況対応力養成(富強国化、国家集約)により、工業の集約化が進んだ。
-
- 第4 流通業(商業)←国土狭・海川移動しやすい
-
-
- 流通業(商業)←国土狭・海川移動しやすい
-
-
- 流通業(商業)←国土狭
- 国土が狭いため移動しやすく流通業(商業)が進んだ。
-
- 流通業(商業)←海川移動しやすい
- 海・川も移動しやすく流通業を進めた。
-
-
- 江戸時代…流通業進む
-
-
- 道路設置・宿設置…流通業進む→全国市場となる→各地の特産品が全国流通
- 道路設置、宿設置(宿場町)され流通業が進んだ。全国市場となった(各地の特産品が全国流通)。
-
- 武士が都市(城下町)に住み消費者となる…流通業進む
- 武士が都市(城下町)に住み消費者となった。
-
- 参勤交代で小国家長(大名)が江戸で多額消費…流通業進む
- 参勤交代で小国家長(大名)が江戸で多額消費したため流通業が進んだ。
-
- 流通業者が都市に住む…流通業進む
- 流通業者も都市に住み流通業が進んだ。
-
- 流通業進む…江戸・大坂が2大商業都市
-
-
- 流通業進む…江戸・大坂が2大商業都市
- 流通業が進み江戸、大坂が2大商業都市となった。
-
- 大坂は米流通業…藩収入の米は大坂で売買
- 大坂は米流通業をした(藩収入の米は大坂で売買)。
-
-
-
- 第5 国家同士流通業(貿易)←銀産国
-
-
- 国家同士流通業(貿易)←銀産国
-
-
- 国家同士流通業(貿易)←銀産国
- 銀産国であったため国家同士流通業(貿易)も古くからした。
-
- 室町・戦国時代に進む
- 室町・戦国時代に進むした。
-
-
- 第6 資金業の集約化
-
-
- 資金業の集約化
-
-
- 資金業の集約化
- 資金業の集約化する。
-
- 室町時代に資金集約始まる…両替商
- 室町時代に資金集約が始まった(両替商)。
-
-
- 江戸時代…流通業者が資金集約→両替商
-
-
- 江戸時代…流通業者が資金集約→両替商
- 江戸時代の流通業者が資金集約(両替商)した。
-
- 江戸豪商…三井・住友・鴻池明治の大財閥
- 江戸豪商がある(三井・住友・鴻池→明治の大財閥)。
-
- 幕府・藩…両替商から借金→藩収支を流通業者に任せる藩も→収入の米を直接両替商に運ぶ
- 幕府・藩は両替商から借金した(藩収支を流通業者に任せる藩も→収入の米を直接両替商に運ぶ)。
-
-
生産役務の発生
- 第1 取引業・流通業の発生
-
-
- 国家長・官僚のもとで取引業・流通業が発生
-
-
- 国家長・官僚のもとで取引業・流通業が発生
- 国家長・官僚のもとで取引業、流通業が発生した。
-
- 国家長・官僚は移動自由→国家長・官僚が取引業・流通業
- 国家長・官僚は自由移動できるから国家長・官僚が取引業・流通業をした。
-
- 国民…国家長・官僚の構成員として取引業・流通業
- 国民は国家長・官僚の構成員として取引業、流通業をした。
-
- 山の口・浜辺・河原(国家長所有)で取引業…市
-
-
- 山の口・浜辺・河原(国家長所有)で取引業…市
- 日本では山の口、浜辺、河原(国家長所有)で取引業、市を開いた。
-
- 天皇に商品を貢納献上(税)
- 山の口・浜辺・河原は天皇領だから天皇に商品を貢納献上(税)。
-
-
-
- 宗教集団のもとで取引業・流通業が発生
-
-
- 宗教集団のもとで取引業・流通業が発生
- 宗教集団のもとで取引業・流通業が発生した。
-
- 宗教者は宗教状況対応の拡大(布教)で自由移動→宗教者が取引業・流通業
-
-
- 宗教者は宗教状況対応の拡大(布教)で自由移動→宗教者が取引業・流通業
- 宗教者は宗教状況対応の拡大(布教)で自由移動できるから宗教者が取引業・流通業をした。
-
- 伊勢神宮・高野山が流通業
- 伊勢神宮・高野山が布教活動として流通業をした。
-
- 立山信仰の修験道者が富山の薬売
- 日本では立山信仰の修験道者が富山の薬売をした。
-
-
- 国民…宗教集団の構成員として取引業・流通業
-
-
- 国民…宗教集団の構成員として取引業・流通業
- 国民は宗教集団の構成員として取引業・流通業をした。
-
- 巫女が神社から往来手形もらい流通業
- 巫女が神社から往来手形もらい流通業をした。
-
-
- 宗教施設で取引業…市
-
-
- 宗教施設で取引業…市
- 取引業は宗教施設で位置を開いた。
-
- 神社・寺の領地で市→農耕業者と工業者が取引
- 神社・寺の領地で市をした(農耕業者と工業者が取引)。
-
-
-
- 国家長官僚・宗教集団のもとの取引業・流通業が終了し独立の取引業・流通業…鎌倉時代
-
-
- 国家長官僚・宗教集団のもとの取引業・流通業が終了し独立の取引業・流通業…鎌倉時代
- 国家長官僚・宗教集団のもとの取引業、流通業が終了し独立の取引業・流通業となった。鎌倉時代である。
-
- 市での営業資格…天皇・公家・寺社に税支払
- 市での営業資格を取得し天皇・公家・寺社に税を支払った。
-
- 近江取引業者(商人)…近江が交通要衝地→取引業・流通業
- 近江取引業者(商人)は近江が交通要衝地だから取引業・流通業をした。
-
- 集団状況対応(取引業者・流通業者同士)…座
- 取引業者・流通業者同士が集団状況対応する(鎌倉時代、座)。
-
-
- 国土狭い→流通業が発生進歩
-
-
- 国土狭い→流通業が発生進歩
- 国土が狭いから流通業が早くから発生し進歩した。
-
- 日本…平野・山・海が接近→農耕業者・漁業者・山人(木工職人・木工品)が接触→流通
- 日本は平野・山・海が接近しているから農耕業者・漁業者・山人(木工職人・木工品)が接触し流通業が進んだ。
-
- 漁業者が船で移動→流通業
- 漁業者が船で移動するので流通業が進んだ。
-
- 日本…遠距離流通→京織物と奥州砂金を交換→多大な成果取得
- 日本の遠距離流通、京織物と奥州砂金を交換では多大な成果取得した。
-
-
- 行商→市→店舗→流通業小国家
-
-
- 行商…取引業者・流通業者が移動して取引・流通
-
-
- 行商…取引業者・流通業者が移動して取引・流通
- 最初は取引業者・流通業者が移動して取引・流通する(行商)。
-
- 近江取引業者(商人)…集団状況対応した→数百人の隊
- 近江取引業者(商人)は集団状況対応した(数百人の隊)。
-
-
- 市…業者と客が集合
- つぎに市になる(業者と客が集合)。
-
- 定地定期市…鎌倉時代
- 市も定地定期市になる(鎌倉時代)。
-
- 店舗…客が業者に訪問(鎌倉時代末期)
- さらに店舗取引業・流通業(客が業者に訪問)となる(鎌倉時代末期)。
-
- 近江取引業者(商人)…楽市楽座で都市に移動し店舗取引→全国に店舗展開
-
-
- 近江取引業者(商人)…楽市楽座で都市に移動し店舗取引→全国に店舗展開
- 近江取引業者(商人)は楽市楽座で都市に移動し店舗取引をした。全国に店舗展開した(独立させる)。
-
- 各地商品を全国販売→運送(飛脚)開始・定宿設置
- 各地商品を全国販売した。運送(飛脚)開始し定宿を設置した。
-
- 資金提供〈投資〉し醸造業おこさせる
- 資金提供〈投資〉し醸造業おこさせた。
-
-
- 流通業小国家設定…惣町・堺
- 集団状況対応(店舗取引業者・流通業者同士)で流通業小国家が設定される(室町時代→惣町、堺)。
-
-
- 第2 工業・役務業の発生
-
-
- 国家長・官僚のもとで工業・役務業が発生
-
-
- 国家長・官僚のもとで工業・役務業が発生
- 国家長・官僚のもとで工業・役務業が発生した。
-
- 国家長・官僚の構成員として工業・役務業…朝廷・貴族・地方豪族の配下
- 国家長・官僚の構成員として工業・役務業をした(朝廷・貴族・地方豪族の配下)。
-
-
- 宗教集団のもとで工業・役務業が発生
-
-
- 宗教集団のもとで工業・役務業が発生
- 宗教集団のもとで工業・役務業が発生した。
-
- 宗教集団の構成員として工業・役務業
-
-
- 宗教集団の構成員として工業・役務業
- 宗教集団の構成員として工業・役務業をした。
-
- 日本は移動自由→木工職人(山人)が神社の氏子となり良材を求めて各地に移動
- 日本は移動自由だから木工職人(山人)が神社の氏子となり良材を求めて各地に移動した。
-
-
-
- 国家長官僚・宗教集団のもとの工業・役務業が終了し独立の工業・役務業…鎌倉時代
-
-
- 国家長官僚・宗教集団のもとの工業・役務業が終了し独立の工業・役務業…鎌倉時代
- 国家長官僚・宗教集団のもとの工業・役務業が終了し独立の工業・役務業となった(鎌倉時代)。
-
- 都市に食い詰めたものが集まり日雇・手伝・芸能
- 都市に食い詰めたものが集まり日雇、手伝、芸能をした。
-
-
- 第3 資金業の発生
-
-
- 資金業の発生
-
-
- 資金業の発生←生産役務が集約高度化すると資金が必要となり資金業発生
- 生産役務が集約高度化すると資金が必要となり資金業が発生した。
-
- 室町時代からの両替商…金銀銭3貨の交換・為替・預金・貸付・手形・公金取扱
- 室町時代からの両替商がある(金銀銭3貨の交換・為替・預金・貸付・手形・公金取扱)。
-
-
大規模集団要因…民族状況対応
- 第1 単一民族
-
-
- 単一民族
- 単一民族である。
-
- 多人種
-
-
- 古日本人…バイカル湖・シベリア東端・中国・インドシナ半島から民族移動
- バイカル湖、シベリア東端、中国北部内陸、インドシナ半島西から民族移動した(最新のDNA鑑定技術で判明←貝塚〈カルシウム〉で溶けなかった古日本人の人骨を鑑定)。
-
- 中国から民族移動
- 中国(多民族)南内陸から海洋民族、遊牧民族が民族移動した(最新のDNA鑑定技術で判明)。
-
- 民族移動状況不明
- 民族移動状況は不明である(流入→日本人は古くから島国との認識ある、遊牧民族は東日本に民族移動せず?→部落差別なし)。
-
- 言語…母音は海洋民族・語順は遊牧民族
- 言語は海洋民族と遊牧民族の双方の要素がある(母音は海洋民族、語順は遊牧民族)。
-
-
- 閉鎖地形(島国)で気候・地形・地質も同じ→同一状況対応→単一民族化
- 閉鎖地形(島国)で気候、地形、地質も同じだから、異なる人種も同じ状況対応となる。単一民族化した(3章状況対応型の分類、1万年以上の縄文時代で、縄文人と流入弥生人が融合)。
-
- 第2 民族移動・民族混在…例外
-
-
- 民族移動・民族混在…例外
- 少ないが民族移動で民族混在がある。
-
- 民族移動…中国人・朝鮮韓国人だけ
- 閉鎖地形だから民族移動は少ない(亡命者・難民少ない)。隣国の中国人、朝鮮韓国人だけである。
-
- 秦設定時の亡命中国人
-
-
- 秦設定時の亡命中国人
- 秦設定時(遊牧民族が国家国土取り込み・強民族支配)に大量中国人亡命者がきた。
-
- 中国の状況対応持ち込み
- 中国の状況対応もちこみした(文化〈娯楽状況対応〉・生産役務対応方法手法〈ノウハウ・営業秘密・技術〉・固定国家状況対応〈国家体制・制度・政策〉)。
-
-
- 朝鮮に亡命した中国人
-
-
- 朝鮮に亡命した中国人
- 朝鮮に亡命した中国人が日本にきた(4〜7世紀)。
-
- 秦氏(秦亡命者)・漢氏(漢亡命者)
- 秦氏(秦亡命者)、漢氏(漢亡命者)がいた。
-
- 中国の状況対応持ち込み…秦氏は養蚕機織り・漢氏は工芸技術
- 中国の状況対応持ち込みした(秦氏は養蚕機織り・漢氏は工芸技術〈鉄器鋳造・皮革加工・金銀細工〉)。
-
- 中国に帰らず日本にきたのは朝鮮が住みにくい?・日本が魅力?
- 中国に帰らず日本にきたのは朝鮮が住みにくい?、日本が魅力?であったのかわからない。
-
-
- 百済・高句麗終了時の亡命朝鮮人←新羅が朝鮮統一
-
-
- 百済・高句麗終了時の亡命朝鮮人←新羅が朝鮮統一
- 新羅が朝鮮統一し百済・高句麗終了(滅亡)のとき大量朝鮮人亡命者(難民)がきた(5〜6世紀)。
-
- 百済人は京都付近…京都は朝鮮人が開拓
- 百済人は京都付近に在住した(京都は朝鮮人が開拓)。
-
- 高句麗人は関東に入植開拓…父系要素
- 高句麗人は関東に入植開拓した(父系要素)。
-
-
- 豊臣秀吉朝鮮国家国土取り込み時の朝鮮人陶工
-
-
- 豊臣秀吉朝鮮国家国土取り込み時の朝鮮人陶工
- 豊臣秀吉が朝鮮を国家国土取り込みしたとき朝鮮人陶工を連れ帰った(国家国土取り込み後自発的に来日の説も)。
-
- 帰国を許したが帰国拒否…生産役務者軽視の本国より日本のほうが厚遇
-
-
- 帰国を許したが帰国拒否…生産役務者軽視の本国より日本のほうが厚遇
- 帰国を許したが帰国拒否した(生産役務者軽視の本国より日本のほうが厚遇、江戸幕府が支援、帰国者は10パーセント以下)。
-
- 朝鮮通信使…10年過ごすうちに財をなして生活が楽になると戻ろうとしなかった
- 連れ戻しに来た朝鮮通信使は「10年過ごすうちに財をなして生活が楽になると戻ろうとしなかった」とした。
-
-
-
- 南宋終了時の亡命中国人
- 南宋終了(滅亡)時(元が国家国土取り込み時)に中国人亡命者がきた。
-
- 明崩終了時の亡命中国人
- 明終了(滅亡)時(清が国家国土取り込み時〉)に中国人亡命者がきた。
-
- 朝鮮合併時の朝鮮人…差別された全羅道(南部)から
- 日本が朝鮮を合併したとき朝鮮人が民族移動してきた(差別された全羅道〈南部〉から)。
-
- 日本第2次大戦敗退時の朝鮮人
-
-
- 朝鮮の朝鮮人官僚…責任追及免れるため
- 日本が第2次大戦敗退したとき日本国家合併時の朝鮮人官僚が責任追及を免れるため民族移動してきた。
-
- 犯罪のため
-
-
- 犯罪のため
- 犯罪をするため民族移動してきた(8章本来状況対応優先・悪質な状況対応基準違反〈犯罪〉)。
-
- 日本で暴力団設定のため…駅前一等地を不法占拠しパチンコ屋
- 日本で暴力集団設定のため民族移動してきた(敗戦混乱日本にヤクザをするため日本に民族移動、駅前一等地を不法占拠しパチンコ屋)。
-
-
-
- 朝鮮合併時・日本第2次大戦敗戦時以降の日本滞在朝鮮人
-
-
- 悪質な状況対応基準違反…犯罪
-
-
- 悪質な状況対応基準違反…犯罪
- 犯罪をする(8章本来状況対応優先・悪質な状況対応基準違反〈犯罪〉)。
-
- 吉田茂…残留朝鮮人の半数は不正入国・犯罪者多数だから本国に返したい
- 吉田茂がマッカーサーに残留朝鮮人の半数は不正入国、犯罪者多数だから本国に返したいと言った。
-
-
- 集団状況対応型の要素→本国朝鮮韓国人が対立争う→半日本人・差別
- 集団状況対応型の要素もあるから本国韓国朝鮮人が対立争う(異なる状況対応は障害→本国朝鮮韓国人が対立争う→半日本人・差別)。
-
-
- 京都・大阪…個人対立争い型の要素
- 古代から中国人・朝鮮人が大量民族移動し京都・大阪に居住した。軽度な多民族状態となった。同化したが個人対立争い型の要素が残る(京都、大阪)。
-
大規模集団要因…集団状況対応型の国家状況対応
集団状況対応型の国家状況対応である(7章国家状況対応)。
個人対立争い型・宗教状況対応型の国家状況対応
(例外・対立争い状況対応のとき)
- 第1 個人対立争い型の要素←対立争い状況対応のとき
-
-
- 個人対立争い型の要素←対立争い
- 対立争いのときは個人対立争い型の要素が出てくる。
-
- 大和政権設定時・戦国時代から江戸時代初期・幕末明治維新
-
-
- 大和政権設定時…国家集約の対立争い
- 大和政権設定時がある(国家集約の対立争い、小国家→集団状況対応〈小国家同士〉)。
-
- 戦国時代から江戸時代初期…小国家長の国家長地位取り合う
- 戦国時代から江戸時代初期がある(小国家長の国家長地位取り合う)。
-
- 幕末明治維新…国家集約の対立争い
- 幕末明治維新がある(国家集約の対立争い、集団状況対応〈小国家同士〉→国家)。
-
-
- 強者支配
- 強者支配する。
-
- 関係設定・状況対応基準制定
- 関係設定、状況対応基準を制定する。
-
- すぐ終了←非本来状況対応
-
-
- すぐ終了←非本来状況対応
- 非本来状況対応だからすぐに終了する。
-
- すぐ強者支配終了←非本来状況対応
-
-
- すぐ強者支配終了←非本来状況対応
- 非本来状況対応だからすぐに強者支配終了する。
-
- 大和政権の強者支配…平安時代に大和政権の公家化
- 大和政権の強者支配は平安時代に大和政権の公家化した。
-
- 戦国時代から江戸初期の強者支配…江戸時代に藩取りつぶしやめる・国家長「良きに計らえ」
- 戦国時代から江戸初期の強者支配は江戸時代に藩取りつぶしやめた、国家長は「良きに計らえ」とした。
-
- 幕末明治維新の薩長強者支配…国会設定で強者支配終了
- 幕末明治維新の薩長強者支配は国会設定で強者支配終了した。
-
-
-
強者支配×
- 第1 強者支配国家×…本来強者支配終了国家
-
-
- 強者支配国家×…本来強者支配終了国家
- 強者支配は非本来状況対応だから、本来強者支配終了国家(自由民主国家)である(国民が古くから自由)。
-
- 国家長の状況対応決定に反対…政治方針反対○→政治の話する○・国家長の話する○・目安箱
- 国家長の状況対応決定に反対してもよい(政治の話する○、国家長の話する○、目安箱)。
-
- 国民が成果取得(土地私有)←国家長成果取得×
- 国家長が成果取得しない。国民が成果取得する。国民の土地私有が古くからある(国民土地私有、国家長は課税権のみ)。
-
- 国会…一体状況対応からすぐ根付く
- 国会制度は一体状況対応から(一体で状況対応決定、国家長・国民が情報交換し合意して状況対応決定する)すぐ根付いた(明治維新、桂首相議会停止命令→国民運動で総辞職)。
-
強者支配(例外)…強者支配方法習得考案
- 第1 強者支配…できにくい→強者支配方法習得考案
-
-
- 強者支配…できにくい→強者支配方法習得考案
- 強者支配できにくい。強者支配には強者支配方法を習得考案がいる(工夫)。
-
- 上皇・院政…関白・大臣に関与させない
- 平安時代の上皇・院政がある(関白・大臣に関与させない)。
-
- 織田信長…家来と合議し自分に合う意見のみ採用した(合議の形骸化)
- 織田信長(初期)は家来と合議し自分に合う意見のみ採用した(合議の形骸化)。
-
- 補助者(官僚以外)おく…江戸時代将軍は側用人おく→官僚に関与させない
- 補助者(官僚以外)をおく。江戸時代の将軍は側用人をおいた(官僚に国家長の状況対応決定に関与させない)。
-
- 権限集中臨時職おく…江戸時代の将軍は大老をおく
- 権限集中の臨時職をおく。江戸時代の将軍は大老をおいた。
-
- 昭和軍人…憲法解釈(統帥権独立)
- 昭和の軍人官僚は憲法解釈(統帥権独立)で、強者支配した。
-
戦国時代から江戸時代初期…強者支配(例外)
- 第1 戦国時代から江戸時代初期…国家が小国家を強者支配
-
-
- 戦国時代から江戸時代初期…国家が小国家を強者支配→織田信長・豊臣秀吉・徳川家康
- 戦国時代から江戸時代初期に国家が小国家を強者支配した(織田信長、豊臣秀吉、徳川家康)。
-
- 状況対応決定…強者支配
-
-
- 国家長が状況対応決定
- 国家長が状況対応を決定する(将軍)。
-
- 小国家長(大名)が状況対応決定×…徳川幕府→外様大名は決定に関与できない
- 大名に状況対応を決定させない(徳川幕府→外様大名は決定に関与できない)。
-
- 天皇(旧国家長)が状況対応決定×
- 天皇(旧勢力、崇拝→権威)に状況対応を決定させない(影響力排除、鎌倉幕府→首都を鎌倉・源氏廃絶・公家将軍の装飾化、江戸幕府→公家妻の子の将軍就任×)。
-
-
- 大名の地位上下制定(小国家上下)
-
-
- 大名の地位上下制定(小国家上下)
- 大名の地位上下を制定した。
-
- 譜代大名>外様大名
- 譜代大名上位、外様大名下位とした。
-
- 旗本>大名…浅野5万石より吉良4000石が高地位
- 旗本上位、大名下位とした(浅野5万石より吉良4000石が高地位)。
-
-
- 国家状況対応力養成優先
-
-
- 国家状況対応力養成優先
- 国家状況対応養成が優先する。
-
- 国家…国家状況対応力養成
- 国家が国家状況対応力を養成する。
-
- 国家…小国家状況対応力養成させない
- 国家が小国家の国家状況対応力を養成させない。
-
-
- 国家…国家状況対応力養成
-
-
- 国家…国家状況対応力養成
- 国家は国家状況対応力を養成する(集約高度化、強国化・富国化)。
-
- 国家対立争い状況対応力養成
- 国家対立争い状況対応力養成を養成する。
-
- 国家生産役務状況対応力養成
-
-
- 国家生産役務状況対応力養成
- 国家生産役務状況対応力を養成する。
-
- 生産役務用地を取得…前国家長の国家収支(財政)基盤を承継→直轄地・鉱山
- 国家が生産役務用地を取得する(前国家長の国家収支〈財政〉基盤を承継、直轄地、鉱山)。
-
-
-
- 国家…小国家の国家状況対応力を養成させない
-
-
- 小国家の国家状況対応力を養成させない
-
-
- 小国家の国家状況対応力を養成させない
- 小国家の国家状況対応力を養成させない。
-
- 参勤交代で藩に消費させ資金集約させない
- 参勤交代で藩に消費させ資金集約させなかった。
-
- 大きい河川に橋設置させず藩に国家集約させない
- 大きい河川に橋設置させず藩に国家集約させなかった。
-
- 徳川家康…藩の弱化・貧化
- 徳川家康は、大名(藩)を弱化・貧化させた(戦国大名富強→幕末大名貧弱)。
-
- その後は強者支配なし…集団状況対応(小国家同士)
- その後は強者支配なかった。集団状況対応(小国家同士)となった。
-
-
- 小国家の国家対立争い状況対応力養成させない
-
-
- 小国家の国家対立争い状況対応力養成させない
- 小国家の国家対立争い状況対応力養成させない。
-
- 小国家の戦争状況対応力養成させない…一国一城・大型船禁止・大砲禁止
- 小国家の戦争状況対応力〈軍事力〉を養成させない(一国一城、大型船禁止、大砲禁止)。
-
- 道路・橋設置×←戦争状況対応力養成させない
- 戦争状況対応〈軍事〉用となる国家基本財産を設置させない(橋×、道路舗装×)。
-
-
- 小国家の生産役務状況対応力養成させない
-
-
- 小国家の生産役務状況対応力養成させない…商品市場統制→江戸大阪市場
- 小国家の国家生産役務状況対応力を養成させない(藩の富化阻止のため商品市場統制→江戸大阪市場)。
-
- 藩収支×←参勤交代
- 藩収支を悪化させる。参勤交代で支出させる(財政弱化→参勤交代〈道中・江戸の消費で経済効果〉)。
-
- 藩収支×←国家集約高度化財産設置(寺院造営・国家長城建設費用負担・河川改修工事)
- 藩収支を悪化させる。国家集約高度化財産設置させ支出させる(寺院造営・国家長の城建設費用負担・幕府城新築修築〈名古屋城の天下普請〉・河川改修工事)。
-
-
-
- 藩の取潰・国替
- 藩の取潰・国替をする。
-
- 第2 戦国時代から江戸時代初期…国家が国民を強者支配
-
-
- 戦国時代から江戸時代初期…国家が国民を強者支配→織田信長・豊臣秀吉・徳川家康
- 戦国時代から江戸時代初期に国家が国民を強者支配した(織田信長、豊臣秀吉、徳川家康)。
-
- 状況対応決定…強者支配
-
-
- 国家長が状況対応決定…将軍
- 国家長が状況対応を決定する(将軍)。
-
- 国民が状況対応決定×
- 国民に状況対応を決定しない。
-
-
- 地位上下制定…階級
-
-
- 地位上下制定…階級
- 地位上下を制定した(7章地位上下)。
-
- 徳川家康…士農工商
-
-
- 徳川家康…士農工商
- 徳川家康は士農工商とした。
-
- 農耕民の固定化…農耕地売買禁止・相続分割禁止
- 農耕民の固定化をした(農耕地売買禁止・相続分割禁止)。
-
- 武士は武装農耕民出身…農耕民の地位上
- 武士は武装農耕民出身だから農耕民の地位上となった。
-
-
-
- 第3 戦国時代から江戸時代初期…国家(強者)が国家状況対応関係設定
-
-
- 国家対内対立争い状況対応させない…関係存続はかる
- 国家対内対立争い状況対応させない(対立争い終了後の秩序回復)。
-
- 国家と小国家(藩)
-
-
- 国家と小国家(藩)の対立争いさせない
-
-
- 国家と小国家(藩)の対立争いさせない
- 国家と小国家(藩)の対立争いさせない。
-
- 人質+対立争いさせない…小国家長(大名)を人質(参勤交代)
- 徳川幕府は小国家長(大名)を参勤交代で人質にした(一定期間ごとに江戸在住)。
-
- 人質+対立争いさせない…小国家長(大名)妻子を人質
- 徳川幕府は小国家長(大名)妻子を人質にした(大名の妻子を江戸で人質に取った)。
-
- 首都攻撃予防…大井川架橋×・船の甲板複数帆柱×
- 徳川家康は首都攻撃を予防した(大井川架橋×・船の甲板複数帆柱×)。
-
-
- 小国家(藩)同士の対立争いさせない
- 小国家(藩)同士の対立争いさせない。
-
- 小国家(藩)同士の提携状況対応させない…大名同士の姻戚関係設定禁止
- 江戸幕府は小国家(藩)同士のの提携させない(大名同士の姻戚関係設定禁止)。
-
-
- 国家と宗教集団
-
-
- 国家と宗教集団の対立争いさせない…寺が藩と対等な力をもった
-
-
- 国家と宗教集団の対立争いさせない…寺が藩と対等な力をもった
- 戦国時代終了後、豊臣秀吉は、寺に対立争いさせなかった(寺が藩と対等な力をもった)。
-
- 過激な浄土真宗抑制…武士に浄土真宗禁止
- 過激な浄土真宗を抑制した(武士に浄土真宗禁止)。
-
-
- 宗教集団同士の対立争いさせない…宗教対立争い×・宗派争い×→改宗派×
- 戦国時代終了後、豊臣秀吉は、寺同士の対立争いをさせない(宗教対立争い×、宗派争い×→改宗派×)。
-
- 寺の対立争い状況対応力養成させない
-
-
- 寺の対立争い状況対応力養成させない
- 江戸幕府は寺の対立争い状況対応力養成をさせない。
-
- 宗派統一(本山末寺制度)させ幕府(寺社奉行)の支配下
- 宗派統一(本山末寺制度)させ幕府(寺社奉行)の支配下においた。
-
- 本願寺を分裂させる…内部対立で弱化
- 本願寺を分裂させた(内部対立で弱化)。
-
-
- 集団状況対応力養成させない
-
-
- 集団状況対応力養成させない
- 江戸幕府は集団状況対応力養成させない。
-
- 信者拡大させない…宗派替禁止
- 信者拡大させない(宗派替禁止)。
-
- 触頭寺院設置…寺を強者支配
- 江戸幕府、藩が設置し各宗派ごとに触頭寺院を設置した。地域内の寺を強者支配した。
-
-
- 宗教集団が成果取得する制度←強者支配させないことをさせない
-
-
- 宗教集団が成果取得する制度←強者支配させないことをさせない
- 江戸幕府は強者支配させないことをさせないため宗教集団が成果取得する制度を制定した(懐柔)。
-
- 檀家制度…葬儀家系管理・戸籍管理
- 檀家制度である(葬儀・家系管理、戸籍管理)。
-
- 寺請制度…寺請証文(住所移転・結婚・旅行)・通行手形発行
- 寺請制度である(住所移転・結婚・旅行→寺請証文〈身分証明〉発行・通行手形発行)。
-
-
-
- 国家と天皇
-
-
- 天皇と藩を提携状況対応させない…大名との姻戚関係設定禁止
- 江戸幕府は提携状況対応をさせない(大名との姻戚関係設定禁止)。
-
-
- 国家と国民
-
-
- 国家長と国民の対立争いさせない…関係存続はかる
- 豊臣秀吉は農耕民(武士輩出)の対立争いさせない(国民の強者支配させない、私戦禁止、兵農分離)。
-
- 武器を持たせない
- 豊臣秀吉は武器をもたせない(刀狩)。
-
-
- 状況対応基準制定・状況対応基準遵守管理
-
-
- 状況対応基準制定・状況対応基準遵守管理
- 状況対応基準制定、状況対応基準遵守管理した。
-
- 状況対応基準制定
-
-
- 儒教導入…強者支配の集団状況対応関係設定
- 徳川幕府は儒教を導入した(強者支配の集団状況対応関係設定)。
-
- 論語・孝・忠・将軍の権威化・忠君(奉国家)をかかげる
- 論語、孝、忠、将軍の権威化、忠君(⇔奉国家)をかかげた。
-
- 取引業者(商人)は生産しないと軽視
- 取引業者(商人)は生産しないと軽視した。
-
- 式目
- 徳川幕府は貞永式目・建武式目を集大成した。
-
- 貞観政要
- 徳川幕府は貞観政要(唐太宗制定)を導入した。
-
-
- 禁中諸法度
- 徳川幕府は天皇一族(皇室)に禁中諸法度を制定した。
-
-
- 国家と国民…状況対応管理→5人組(相互監視・連帯責任)
- 豊臣秀吉が5人組を制定した(相互監視・連帯責任)。
-
江戸時代の改革…強者支配(例外)
- 第1 江戸時代の改革(強者支配)…国民の状況対応決定
-
-
- 江戸時代の改革(強者支配)…国民の状況対応決定
-
-
- 江戸時代の改革(強者支配)…国民の状況対応決定
- 江戸改革時代の改革(強者支配)がある。
-
- 徳川綱吉…生類憐れみの令・勤勉倹約
- 徳川綱吉の生類憐れみの令(戦国時代で殺人平気→動物殺害すらさせない状況対応基準)、勤勉倹約がある。
-
- 徳川吉宗…享保の改革→倹約令・農耕民増税
- 徳川吉宗の享保の改革がある(倹約令・農耕民増税)。
-
- 松平定信…寛政の改革
- 松平定信の寛政の改革がある。
-
- 水野忠邦…天保の改革
- 水野忠邦の天保の改革がある。
-
- たまの強者支配で人気
- たまの強者支配で人気がでた。
-
-
- 生産役務集約高度化制御←強者支配
- 生産役務集約高度化を制御した(工業・商業制御←農耕業重視、景気×)。
-
- 強者支配しない田沼意次が不人気
-
-
- 強者支配しない田沼意次が不人気
- 強者支配しない田沼意次が不人気であった。
-
- 田沼意次は生産役務状況対応力養成した…農耕業から商業(取引業・流通業)へ
- 田沼意次は生産役務状況対応力養成した(農耕業から商業〈取引業・流通業〉へ)。
-
-
昭和軍人官僚…強者支配(例外)
- 第1 昭和軍人官僚…強者支配
-
-
- 昭和軍人官僚(青年将校)…強者支配
- 昭和軍人官僚の強者支配がある(青年将校)。
-
- 日本第2次大戦敗戦
- 日本第2次大戦敗戦した。たまの強者支配で人気がでた。
-
国家状況対応関係本来設定・状況対応基準本来制定
- 第1 国家状況対応関係本来設定・状況対応基準本来制定
-
-
- 本来国家状況対応関係設定
- 集団状況対応型は本来国家状況対応関係設定である。
-
- 本来国家状況対応基準制定…内蔵
- 集団状況対応型は本来状況対応基準制定である(内蔵)。
-
- 状況対応基準は心構え←本来状況対応基準制定(内蔵)
-
-
- 状況対応基準は心構え←本来状況対応基準制定(内蔵)
- 本来状況対応基準制定(内蔵)だから日本の制定状況対応基準は心構えに過ぎない。
-
- 聖徳太子の憲法
- 聖徳太子の憲法がある。国家長・官僚の心構えに過ぎない。
-
- 鎌倉幕府…武士諸法度
- 鎌倉幕府は武士諸法度を制定した。
-
- 室町幕府…礼法格式
- 室町幕府は礼法格式を課した(小笠原流)。
-
- 江戸幕府…儒教を導入
- 徳川幕府は儒教を導入した(本節戦国時代から江戸時代初期強者支配〈例外〉)。
-
-
関連記事
前へ
22節 強者支配…強者支配の程度・連鎖
次へ
23節 日本(2)